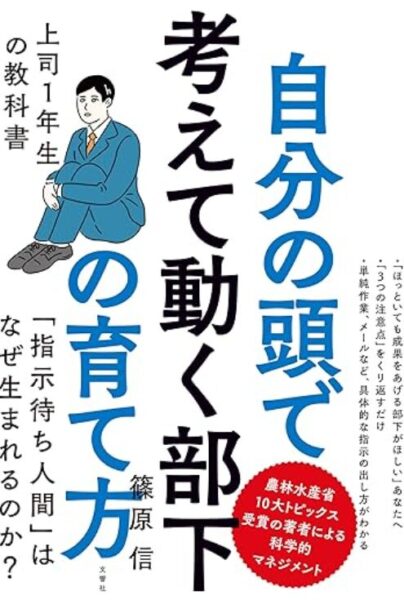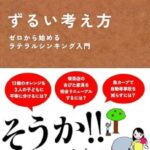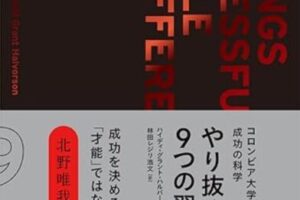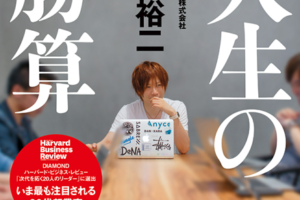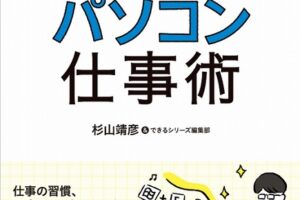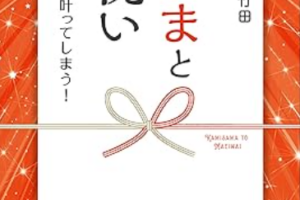こんにちは、やつお(@yatsu_o)です。
あなたは、リーダーとして「部下がなかなか自主的に動いてくれない…」と悩んだことはありませんか?
篠原信氏の著書『自分の頭で考えて動く部下の育て方 上司1年生の教科書』は、そんな上司に向けて「指示待ち人間を作らないための指導法」を説いた一冊です。
本記事では、本書を読んで学んだ重要ポイントを紹介しながら、「部下が主体的に動くために上司がすべきこと」を考察します。
※およそ2分で読めます
【書評】『自分の頭で考えて動く部下の育て方』|指示待ち部下を生まないためのリーダー論
優秀な人ほど指示待ち部下を作りやすい
「細かい指示を出すのが得意な上司ほど、指示待ち部下を生んでしまう」
本書では、この矛盾を鋭く指摘しています。
指示を出しすぎるデメリット
指示を細かく出しすぎることで、次のような問題が発生します。
-
部下の考える力を奪う
→「指示がなければ動けない」という依存体質が形成され、上司の負担が増加する。 -
部下のモチベーションが低下する
→ 指示に従った結果ミスをした場合、部下は消極的になる。
歴史に学ぶ「指示の弊害」
本書では、三国志の孔明と馬謖のエピソードが紹介されています。
孔明は馬謖に「陣地を山上に築いてはならない」と何度も指示しました。
しかし、優秀な馬謖は「そんな当然のことを何度も言われる」ことに反発し、あえて指示を無視。
その結果、戦いに敗れました。
このエピソードから分かるのは、「優秀な人ほど、細かい指示を嫌う」ということです。
指示待ち人間を作らないためにすべきこと
では、部下の主体性を育むために、上司はどうすればよいのでしょうか?
「ちょっとダメな上司」を演じる
優秀な上司ほど、何でも先回りして答えを出してしまいがちです。
しかし、本書ではあえて「少し頼りない上司」を演じることで、部下に考えさせることの重要性が説かれています。
例えば、部下に質問された際、すぐに答えを出すのではなく、こう返してみましょう。
-
「君ならどうする?」
-
「こういう場合はどう対応すべきだと思う?」
部下自身に考えさせることで、「指示待ち」から「自発的に動く」習慣が身についていきます。
指示は「最小限」に留める
仕事の方向性や目的を示すことは大切ですが、「細かい指示」は逆効果。
例えば、次のような伝え方をすると、部下の自主性が育ちます。
☓ 悪い例(細かすぎる指示)
「この書類をA4サイズで印刷して、フォントは12pt、タイトルは太字、余白は2cm取ってね。」
〇 良い例(目的を伝える)
「読みやすい資料を作ってほしい。レイアウトは工夫してみて。」
こうすることで、部下が「どうすれば読みやすくなるか」を考え、主体的に動くようになります。
「教えない教え方」が部下を育てる
本書の核心ともいえるのが、「教えない教え方」という考え方です。
教えすぎないことが成長につながる
著者は、「最も効果的な指導法は、あえて答えを教えないこと」だと述べています。
私自身も、学生時代に数学が苦手で、友人に質問したことがありました。
しかし、友人は「教科書を読めばわかるよ」としか答えてくれませんでした。
当時は「冷たいな」と思いましたが、今振り返ると、彼の対応こそが最適な学びの方法だったと気づきました。
「自分で考え、答えを導き出す」経験が成長につながる
これこそが、本書が伝えたいメッセージです。
まとめ:リーダーが意識すべき3つのポイント
『自分の頭で考えて動く部下の育て方』を読んで、特に印象的だったのは以下の3点です。
-
指示を出しすぎると、部下は指示待ち人間になる
-
あえて「少し頼りない上司」を演じ、部下に考えさせる
-
「教えない教え方」が部下の成長を促す
部下を育てることは、短期的には手間がかかります。
しかし、長期的に見ると、自主的に動ける部下が増え、組織全体の成長につながるでしょう。
リーダーとして、あなたの指導方法を見直すきっかけになれば幸いです。
📖 『自分の頭で考えて動く部下の育て方 上司1年生の教科書』をチェック 👉 Amazonで見る
さいごまで読んでいただき、ありがとうございました。