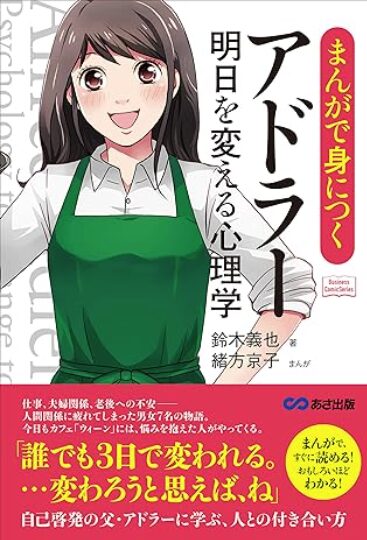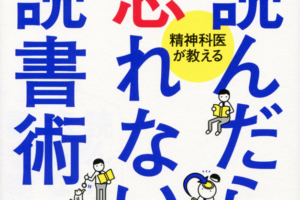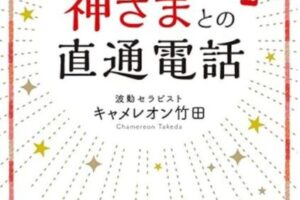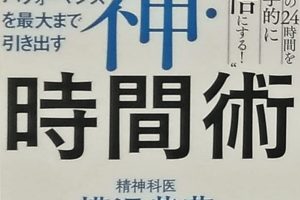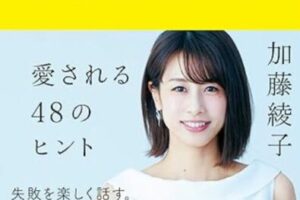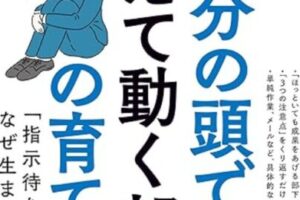こんにちは、やつお(@yatsu_o)です。
精神科医・心理学者として“自己啓発の父”と呼ばれるアルフレッド・アドラー。
名前は知っていても、「難しそう」と敬遠していた方も多いのではないでしょうか?
私自身も、そう考えていました。
しかし、『まんがで身につく アドラー 明日を変える心理学』を読み、考え方が大きく変わりました。
今回は、この一冊を通じて得た気づきをご紹介します。
※およそ2分で読めます
【書評】まんがで学ぶアドラー心理学|自己肯定感が高まる“明日を変える”思考法
劣等感と優越感は“裏返し”
たとえば、体格も運動能力も自分より上回る兄がいるとします。
すると、どうしても「自分は兄より劣っている…」と感じることでしょう。
アドラーはこれを “主観的な劣等感” と呼び、それに対して「優越感で補おうとする心理」が生まれると説いています。
この2つの感情は表裏一体。
私たちが無意識に他人と比較してしまうのは、自己評価を保ちたいという心理の表れなのかもしれません。
しかし、アドラー心理学では、「比較ではなく、自分の人生に集中する」ことの重要性が説かれています。
個人的にも、「他人と比べるより、自分が熱中できることに全力を注ぐほうが遥かに有意義だな~」と強く感じながら生きています。
人生の課題にどう向き合うか
アドラーは人生の課題(ライフ・タスク)に対する向き合い方を2つに分類しています。
-
有益な側面:主体的・能動的・挑戦的
-
無益な側面:受動的・劣等感や優越感に囚われる
日本では、謙虚さが美徳とされる反面、消極的・受動的な態度が根付いているように思います。
私も「やったほうがいいけど、自信がない…」と、行動をためらった経験が何度もあります。
しかし、実際は「行動しておいたほうが物事がうまく運んでいたのに…」と後悔することのほうが圧倒的に多かったのです。
そのため、普段からアドラー心理学を実践し、前向きに課題と向き合う姿勢を身につけることが重要なことは疑う余地がありません。
他者の期待を生きるのではなく、自分の人生を生きる
アドラー心理学の根底には、「他者の期待に応えることは自分の課題ではない」という明確な線引きがあります。
職場や家庭で「責任を押し付けられてつらい」と感じている方は多いはず。(私もその一人でした)
しかし、アドラーの言葉に出会い、自分が背負う必要のない責任があると気づけたことは大きな学びです。
「自分や家族のために生きる」という価値観は、自己犠牲の人生からの解放でもあります。
完璧を目指さない“勇気”が、行動を後押しする
アドラー心理学では「不完全である勇気」も重要なキーワードです。
ブログ運営をしている私にとっても、この言葉は非常に刺さりました。
完璧主義に陥ると、1記事仕上げるのに何日もかかり、結果的に行動が止まってしまいます。
精神科医の樺沢紫苑先生も「60点でいいから、まず行動することが大事」と提唱しており、この考え方に支えられて、私はブログ運営を続けられています。
あとがき|アドラー心理学が教えてくれる“幸せ”の本質
本書では他にも、「共同体感覚」という概念が登場します。
人とのつながりの中で、信頼と尊重を育むこと。
それこそがアドラーの言う“真の幸せ”です。
富や名声よりも、人間関係の質に重きを置くこの考え方は、現代のストレス社会において、私たちにとって大きなヒントになるはずです。
「アドラー心理学って難しそう…」と感じている方こそ、本書から学べることは多いと思います。
マンガ形式で読みやすく、心理学初心者にもおすすめです。
📖 『まんがで身につく アドラー 明日を変える心理学』をチェック 👉 Amazonで見る
さいごまで読んでいただき、ありがとうございました。